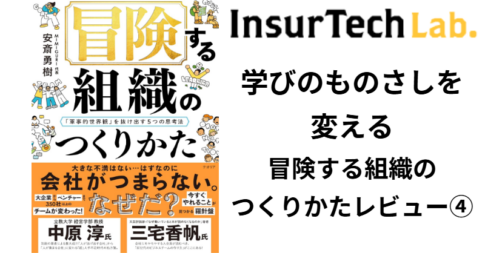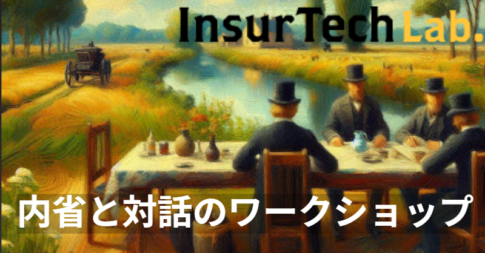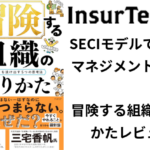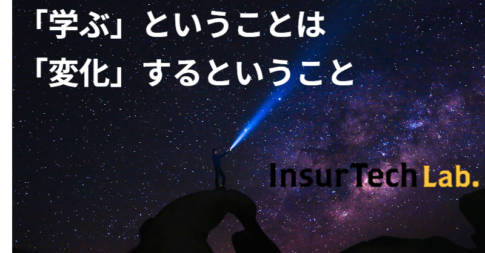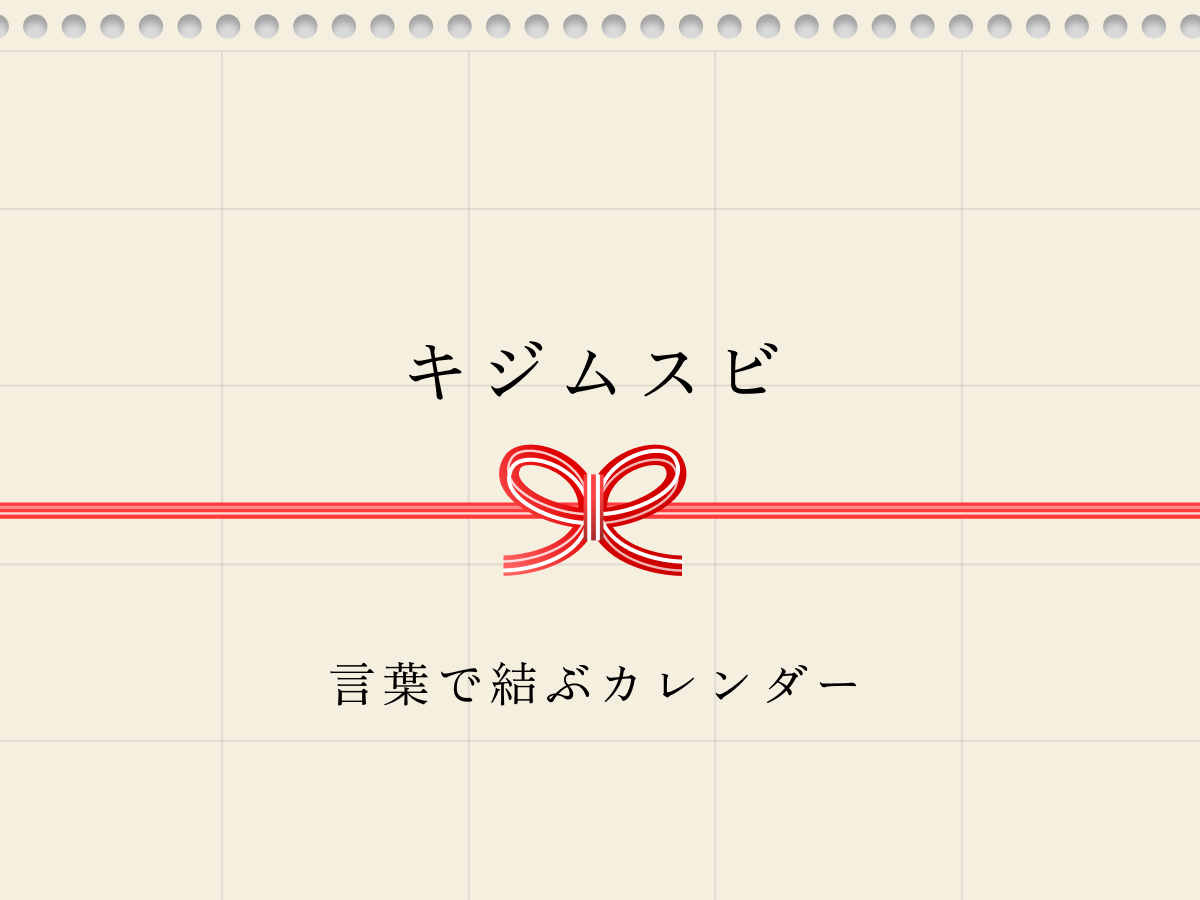昨日に引き続き、安斎さんの「冒険する組織のつくりかた」をもとに、これまで実践した施策を振り返り、今後の方向性を整理します。本日は『KEY11「ハレの場としての『全社総会』に命をかける」』です。
ちなみに昨日の記事はコチラです。
1. はじめに:「組織のアイデンティティ」をどう作るか
組織のアイデンティティは、日々のミーティングや1on1といった「ケ」の場だけでは生まれません。もちろん、日常のコミュニケーションは重要ですが、それだけではメンバーの中に「組織を主語としたアイデンティティ」は醸成されにくいです。
そこで必要になるのが、非日常の「ハレ」の場です。安斎勇樹さんの『冒険する組織のつくりかた』では、全社総会を「ハレの場」として位置づけ、組織の探究の整合をつなぎ直す場として活用することの重要性を説いています。
私たちは全社総会という会社全体の仕組みにはリーチできませんが、自分の組織に関して同様にハレのイベントを実施しています。四半期ごとに実施しているキックオフミーティングや対面イベント移管して、本記事では、その取り組みを紹介しつつ、「ハレの場」の意義について考えていきます。
2. 「ハレの場」としての四半期キックオフと対面イベント
四半期ごとのキックオフミーティングと対面イベントは、私たちの組織にとってチームの方向性を再確認し、探究心を高めるための貴重な機会です。
- 対話に力を入れる:対面イベントでは、単なる報告会ではなく、メンバー同士が深く対話し、互いの考えを理解し合う場を作ることを重視しています。
- 発表・フィードバックの場を設ける:自分たちの探究テーマやチームの活動・興味のあることを発表し、それに対するフィードバックを受ける場とすることで、発信/フィードバックの文化醸成を目指します。
- リーダーや運営の想いを語る:組織のビジョンや方向性をストーリーテリング形式で共有し、メンバーが共感しやすい形で伝えるようにしています。
この「ハレ」の場を活用し、メンバーが探究活動を加速し、探究や発信を意識する文化を醸成することを目指しています。
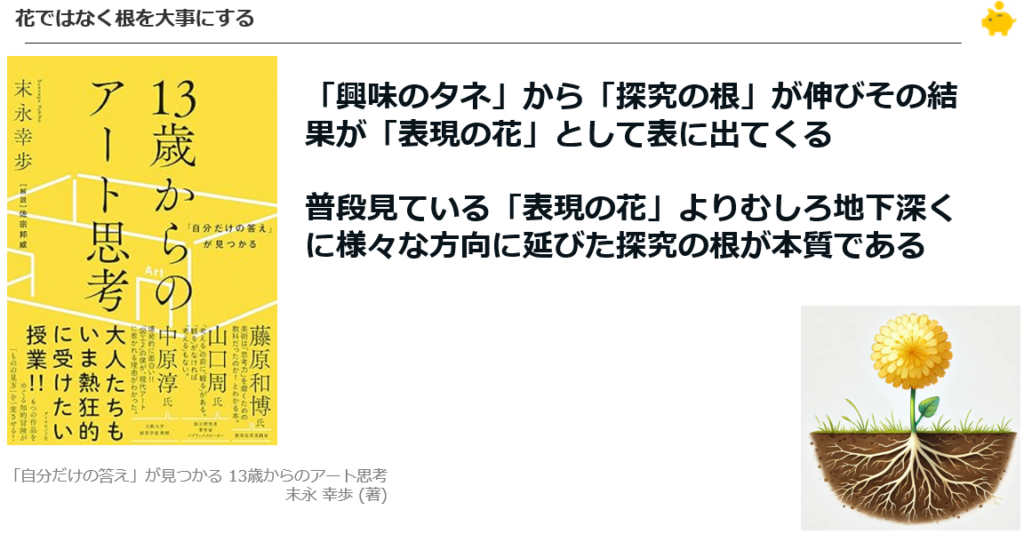
3. 「ストーリーテリング」が組織の探究をつなぐ
『冒険する組織のつくりかた』では、全社総会における「ストーリーテリング」の重要性が強調されています。単なる業績報告や計画発表ではなく、「どのような探究の試行錯誤があり、それがどのように結果につながったのか?」というストーリーを語ることが組織のアイデンティティ形成に不可欠です。
リーダー自身が探究のプロセスを率先して語ることも重要と記載されています。私自身も社外登壇やブログ発信を行っているため、その内容を元に個人や組織の探究の進捗を共有し、メンバーの探究心を刺激するようにしています。
参考
4. 対話の場を設計する
安斎さんの提唱する全社総会では、メンバー同士の対話の時間を確保することが強調されています。対話のきっかけとなる「問い」を用意し、ただ話を聞くだけではなく、能動的に考え、対話を深めることが重要です。
私たちの対面イベントでも、チームワークショップを重視しています。テーマはその時々の状況で変えていますが、今後はより「問い」の作成に力を入れて、メンバー同士の対話が活性化していきたいと思います。
5. 今後の課題
本書の内容も踏まえて下記については検討課題だと感じています。
個人‐チーム‐組織の整合について
本書ではCCMの強化ポイントが3カ月で一巡するようローテーションを組み、たとえば、1か月目は「社会的ミッション探究と事業ケイパビリティの探究」のつながりに重きを置き、次の1ヶ月はまた別の整合と、整合のポイントを変えながら実施しているとのことでした。
こういったサイクルにすることで、有効度もあがりますし企画する方の負荷も減ると思います。我々はわりと現状を踏まえて行き当たりばったり?でテーマを決めているので、この考え方は参考にしたいと思いました。
対面イベントの時間について
四半期のイベントについては基本的には半日にしています。ただ、年に1回や半年に1回等は、1日かけるイベントなど、長さは調整したいと思いました。いつかは合宿的な取り組みも全員巻き込んでやってみたいです
6. まとめ:私たちにとっての「ハレの場」
全社総会に限らず、組織の整合を高めるためには「ハレの場」を設計することが不可欠です。私たちは四半期ごとのキックオフと対面イベントを活用することで、日常業務では得られないつながりや探究心を共有する機会を作っています。
これらを意識することで、単なる業務の進捗確認の場ではなく、組織の成長を加速させる「ハレの場」を作り上げていきたいと思います。現在は我々の組織だけで実施していますが、もっと上位組織や会社全体にリーチできるように少しずつ巻き込んでいきたいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。