現在、私たちのチームでは、スプリント期間を1日で設定し、”々回しています。
また、2チーム同時に運営しており、LeSSの”1POで複数チーム”という運用に近い進め方をしています。
1dayスプリントをうまく回すためにはゴール設定とレビューでの検査適応がレバレッジポイントだと思っていて、ゴール設定についてチームで上手くなろうと取り組みを続けてきました。
まだ、新たな運営を始めてから1ヶ月ですが、現在のゴール設定の仕方やスプリントプランニングのアジェンダについて紹介します。
スプリントプランニングアジェンダ
下記アジェンダで毎日実施しています。毎日Gather(バーチャルオフィス)に集まって9:00からオンラインで実施しています。
デイリースクラムとスプリントプランニングを融合させた形で実施しています。
1~5までは2チーム横断で実施して、6のToDo出しでチーム毎に分かれるような運営をしています。特徴的な運営としては1の「アイスブレイクでの自己紹介」と、4の「スプリントゴールの設定&確認」だと思います。
アイスブレイクでの自己紹介
チームで運営していく上ではベースとして個人個人の特性を一定知っていることが望ましいと考えており、最初に簡単な自己紹介を実施しています。(毎日1人ずつ実施して何周か行っています)毎日この時間に結構なコストをかけていますが、大事なことだと考えています。
関係の質を上げることで、結果があがっていく良いループが出来ると考えており、そういった個人を知る作業を大事にしています。詳しくは下記記事で解説しています。
今の所は上手くいっていると思っています。今までは「偏愛マップ」や「みんなで記者会見」等個人を知る活動が中心でしたが、これからは「好き嫌いマップ」や「ドラッカー風エクササイズ」等チームの中でどう自分が活躍するか?といった自己紹介を重視していこうと考えています。
スプリントゴールの設定
スプリントゴール設定については力を入れている取組で、下記アジェンダで進めています。
①.PBIを見て優先順位の高いものを見ながら、実施しそうなタスクを確認しよう
②.スプリント後のステークホルダーの状態を妄想しよう
③.状態のなかでの優先度を考えよう(投票)
④.ゴールを文書化しよう
⑤.ゴールに対してFiveFingerでしっくり度を表明しよう
⑥.スプリントレビューをイメージアップしよう
⑦.スプリントゴールを達成できるバックログを選ぼう
①.PBIを見て優先順位の高いものを見ながら、実施しそうなタスクを確認しよう
デイリースプリントなので1日に実施できる量は限りがあります。場合によっては1つのバックログを分解しないとならないケースも発生します。そんな中で、並んでいるバックログを上から実施するだけでは、単なるタスクの履行となってしまうため、「今日、どんな価値を得るのか?」という集中できるゴール設定が重要となります。
とはいえ、いきなり好きにゴール設定しても現実と乖離してしまうため、まず上の方から並んでいるバックログを何個か眺め、この辺をやるのかな?やれるかな?とメンバー各自で考える所から始めています。
②.スプリント後のステークホルダーの状態を妄想しよう
①でいくつかのバックログについて考えた後、それらも踏まえながら今日終了後にステークホルダーにどんな価値を与えたいか?どんな状態にしたいかを妄想します。ステークホルダーを横に並べて、その下に『〇〇〇を実施して、△△△にしたい』といった形で今日の状態を妄想しています。
ステークホルダーについてはあらかじめ「自分たちのチーム」「レビューに参加する他チームの人」「上位者/承認者」「エンドユーザー」「購買決定者(chooser)」といった基本的なステークホルダーは上げておきながら、その人たちに今日1日でどんな変化をもたらしたいか、メンバーで妄想しながら書いています。
こちらのワークは下記サクセスファクターのワークショップを簡易にした形で実施しています。
また、デイリースプリントだと、その日得られる価値は限定的になるので、あまり達成できるかどうかは気にせず、多少遠い未来のゴールであっても、妄想的に広く描くことを推奨しています。」
③.状態のなかでの優先度を考えよう(投票)
上記記載したステークホルダーの状態に対して、ワクワクするゴール(目指すことで力が生まれる)の軸でメンバーで投票しています。ゴール設定をするのとしないので、1日の結果が変わらないのであれば、ゴール設定の意味はありません。そういった意味で、少しでも内発的動機をくすぐる軸で興味を持てるものを投票してもらっています。

④.ゴールを文書化しよう
上記投票してもらったものを参考にしながら、具体的なスプリントゴールの文面を作成しています。
ゴールの記載のフォーマットについては、GOAL(達成すること)とJOY(その時に嬉しい状態)を分けて書いています。GOALとJOYの記載については2024年のScrum Fest Osakaの資料を参考にしています。
ゴールを作成する際には、SMART、ALIVE、FOCUSといったゴール設定のポイントも参考にしながら作成しています。(ALIVEは「冒険する組織のつくりかた」より、FOCUSは「スプリントゴールで価値を駆動しよう」からとっています)
また、それらのゴール軸を踏まえた簡単なチェック項目も作ってみました。
ゴールの文書化は時間の都合上POが文書化することが多いですが、明確に誰が文書化すべきかは決めてません。ただ、毎日の限られたプランニング時間内でゴール設定しており、あまり時間もかけられないので、とりあえず素早く文書化して、あとは、毎日作る中でちょっとずつゴール設定のレベルが上げられるように練習していけばよいと思っています。
SMART , ALIVE , FOCUS
Specific:具体的である
Measurable:測定可能である
Achievable:達成可能である
Relevant:上位目標と関連する
Time-bound:時間起源がある
Adaptive:変化に適応できる
Learningful:学びの機会になる
Interesting:好奇心をそそる
Visionary:未来を見据える
Experimental:実験的である
Fun:楽しさの要素を入れ、覚えやすいタイトルにする
Outcome-Oriented:成果指向のゴールにする
Collaborative:チーム全体で作成する
Ultimate:究極的な理由(WHY)を含める
Singular:単一の明確なゴールを設定する
下記が簡単な良いゴールの評価表です。
1.チーム全員が「今日のゴールは○○だよね」と即答できるか?
・ゴールが明確かつチーム全体に共有されているかを確認
2.JOYの具体イメージや「成果(Outcome)」の認識があるか?
・ タスクではなく、成果(レビュー等で誰がどう嬉しいか)がイメージアップできているか
3.ゴールがあることで、無い場合よりも変化がありそうか?
・ゴール達成に関して、バックログを変更できる可能性はあるか?
・ストレッチゾーンを感じられそうなゴールか?ゴールを設定したことで学びが増えそうか?
4.ワクワク感や意味づけが含まれているか?
・「ゴール」のディスカッションの中で思わず前のめりに、心が動く経験があったか?
・ゴールを作るプロセスで、チーム全員が対話に参加できたか?
5.ゴールの達成/未達が分かるものか、1日で達成可能なスコープか?
・ゴール達成/未達がわかるか?過去の天気を踏まえて「ちょいチャレンジ」くらいの現実性があるか?
6.ゴールが「プロダクトゴール」や中長期ビジョンと繋がっているか?
・今日のスプリントが、どのように全体戦略やロードマップに貢献するのか見えているか?
⑤.ゴールに対してFiveFingerでしっくり度を表明しよう
作ったゴールに対してメンバーとしてどの程度コミットできるか、Five Fingerで表明します。1:コミットできない~5:フルコミットまで、メンバーにそれぞれ数字で表明してもらい、その後、何人かにどうしてその数値になったかしゃべってもらい、必要があれば④の文書化の修正を行います。表明する軸は、『ゴールがワクワクするか? & 実現可能性はあるか?』の統合した軸となります。
補足)コミットメントについて
・スクラムの価値基準でも確約(commitment)があります。我々は確約(commitment)については、確実にやり遂げると宣言することではなく、下記にあるような、『ゴールを公言して聞いている全員が肯定的に受け止めている事』と捉えるようにしています。
・いったん言葉に出して話してみて、自分の耳で聴いてはじめて、「ああ、自分ってこんなこと考えていたんだ」「こうすればいいんだ」という気づきが起きてくれるのです。(これを「オートクライン」(autocrine)と呼びます。)
・生徒たちは自分の作文を全員の前で発表しました。こんなふうに、自分の目標やゴールを発表することを、コーチングでは「コミットメント」(公言)と呼んでいます。「わたしはこれをします!」と口に出して宣言する。その宣言を聴いている全員が「この人はそれを成し遂げる人だ」と肯定的に受け止める。これがけっこう重要なことなのです。
「やってみよう! コーチング」より引用
ゴールについては、その達成・失敗よりも得られた価値が大事だと考えています。
たとえば、
「A.100万円の売上目標に対して200万円GET」
「B.1000万円の目標に対して500万円GET」
を比べると、ゴール未達のBの方が価値が大きいと考えます。チームにとって意味のあるゴールを公言して、それに集中することが、何よりも大切だと考えています。
⑥.スプリントレビューをイメージアップしよう
上記ゴールを踏まえ、今日のスプリントレビューでのアジェンダを考えます。あくまでも実施前なのでアジェンダ変更はあるかもしれませんが、ゴール設定して当日夕方のレビューで何をするかイメージがついていない場合は、そのゴールはだいぶ怪しいです。
具体的なレビューアジェンダを決めることで目標と実施内容の整合について、一定検査することが出来ます。
⑦.スプリントゴールを達成できるバックログを選ぼう
今までの内容を踏まえ、実際に実施するバックログを選びます。ここまでくるとバックログを選んだり、実は足りないバックログが見つかりバックログを追加することが出来ます。最後に昨日の天気(ベロシティ)の状態から出来そうか確認して、合同でのプランニングは終了となり、チーム毎のSBIの精緻化に移っていきます。
実施しての感想/状況
デイリーでスプリントを実施する際の決め手がこのゴール設定だと考えています。ゴール設定が上手くいけばスプリントの検査適応が機能しますし、ゴール設定が微妙だと、例えばバックログの履行が進んだとしても検査・適応が上手く回らないと感じています。
(合わせて検査するためにはスプリントレビューのカイゼンも必要だと考えており、プランニングとレビューを合わせてどう改善するかが非常に重要となります。)
実際、私たちのチームでは、この1ヶ月を以下のように進めてきました。
最初は「デイリーでスプリントなんて無理ではないか?」とメンバーの反対も多かったですが、今ではメンバーの満足度も高く実施できていると思います。
1週目:とりあえず型通り実施してリズムを作る。メンバーは満足。
2週目:型はこなせていくが、ゴール設定の意味について疑問を持つ(基本ゴールは毎回達成だった)
3週目:ゴールの意味合い等の勉強会もしながらゴール設定を改善。ゴールについて未達成の会も増える。試行錯誤
4週目:ゴール設定は一定カイゼン。今度はスプリントレビューの検査について課題に上がる
毎週何らかの成長と問題に気づいて進めていけているので良い感じで学習できていると感じています。
また、ゴールについての「勉強会」については、色々な書籍を紹介し、「良かった」といった声もあった一方、「消化しきれなかった。」といったメンバーの声もあったので、また適宜修正しながら、引き続き良いゴールの作り方の言語化に取り組んでいき、また展開したいと思います。
読んでいただきありがとうございました。







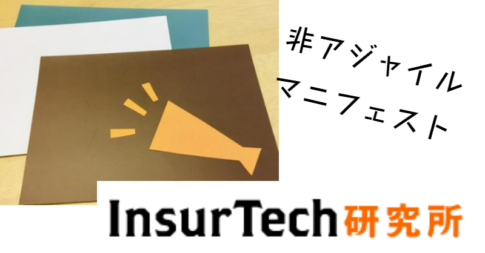
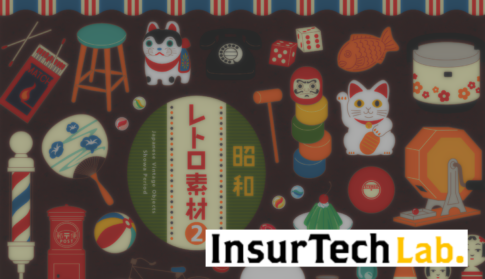

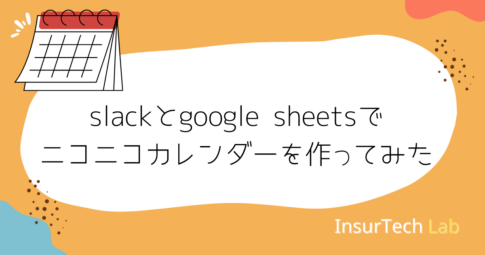
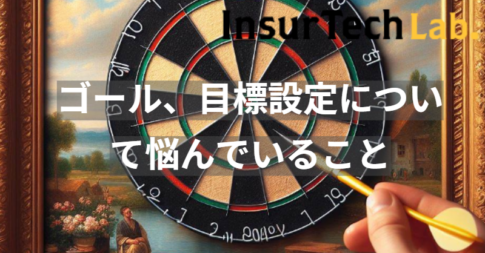
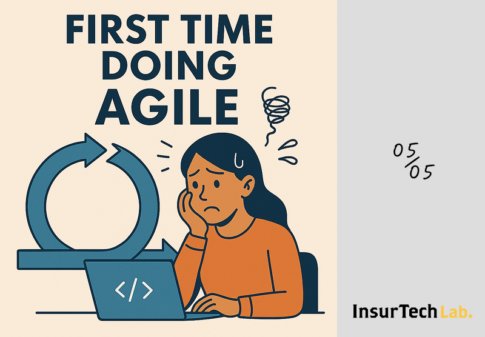
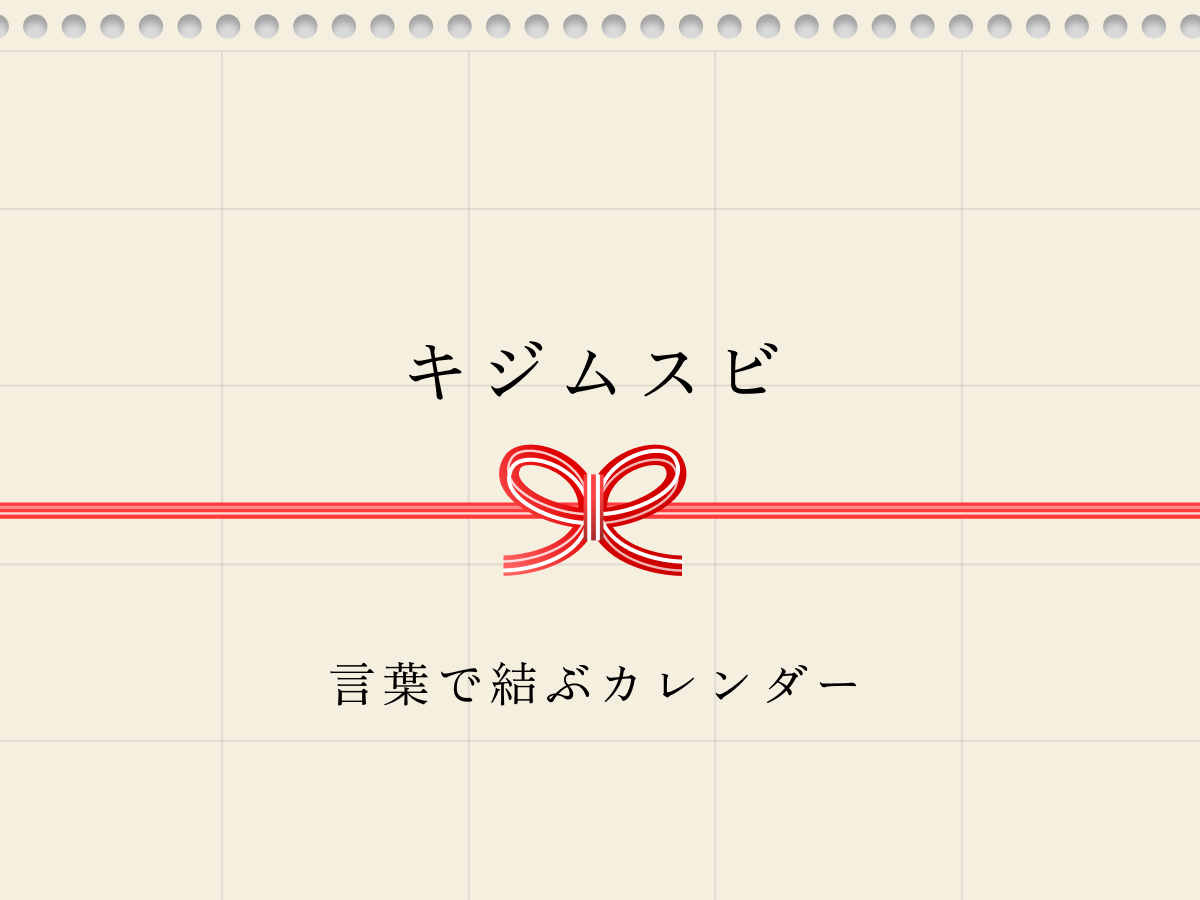

1.アイスブレイク(自己紹介)(7分)
2. よろず確認/今日のMT,不在確認 (4分)
3.前回スプリントのレトロ&バックログ消化の確認 (4分)
4.スプリントゴールの設定&確認 (20分)
5.チーム横断での確認事項 (2分)
6.チーム毎に分かれてスプリントバックログの確認、ToDo出し (20分)