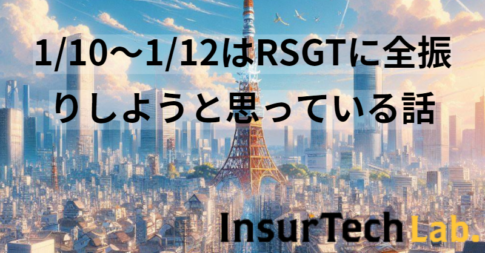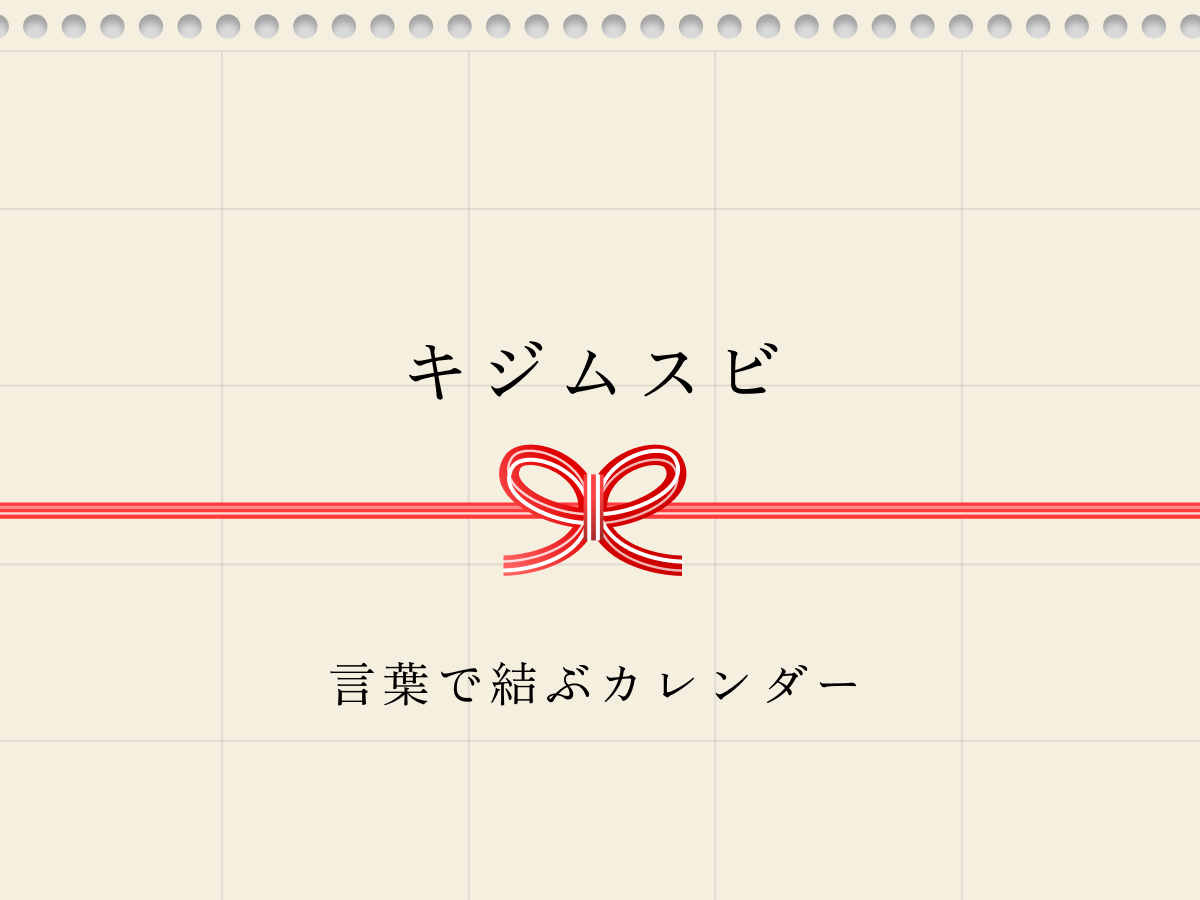今回は「KEY13 育成の要である『フィードバック』の質を変える」について考えます。本書の内容を引用しながら、冒険的な学習文化を定着させるために必要なフィードバックの在り方について紹介します。ちなみに前回の記事はコチラになります。
1. フィードバックの質が学習文化を左右する
安斎氏は本書の中で、「冒険的な学習文化を定着させるうえで一番手っ取り早い方法は、日常的に行われているフィードバックの質を変えることです」と述べています。従来の軍事的世界観におけるフィードバックは、組織内で求められる水準のパフォーマンスを発揮できるよう技術をインストールすることに重きが置かれていました。そのため、望ましくない行動が見られた場合、上司は直ちにそれを改めさせる必要があったのです。
一方で、冒険的世界観におけるフィードバックは、相手がまだ気づいていない「未来の可能性」を提示することを重視します。安斎氏は「じつはこんなこともできるかもしれない」という新しい冒険の道に気付かせることこそが、冒険的なフィードバックの本質であると強調しています。これは単なる問題点の指摘ではなく、相手の成長を促すための未来志向型の提案なのです。
この話はカルティベースラジオで話していた「ポテンシャルフィードバック」の話が事例としてはとても分かりやすいと思っています。
2. フィードバックを未来志向型に変える方法
2.1 相手の内的動機に向き合う
本書では、「フィードバックの本質は、部下の内的動機や探究テーマに共に向き合い、それを外的価値と整合させる方法を一緒に考えること」にあると述べられています。これは単に業務遂行のための指摘ではなく、個人の成長と組織の目標を両立させるためのプロセスです。
2.2 適切なタイミングで行う
フィードバックは即座に行われる必要がないことも強調されています。安斎氏は、「相手が新しい目標を設定しようとしていたり、壁に行き詰って視野が狭くなっているときなど、しかるべきタイミングを見計らってコミュニケーションを取る方が効率的である」と述べています。相手が受け入れる準備ができている瞬間を見極めることが、フィードバックの効果を最大限に引き出す鍵となります。
2.3 「ものの見方」を広げる言葉を使う
冒険的なフィードバックでは、「相手の『ものの見方』を広げる言葉を大切にすること」が重要とされています。これにより、相手は自分の視野を広げ、新しい視点から課題を捉え直すことができます。
3. フィードバック文化を組織全体に浸透させる
3.1 フィードバックの双方向性を重視する
安斎氏は、「フィードバックは部下から上司へはもちろん、チームのメンバー同士でも、上司に対してもどんどんフィードバックし合うことが推奨される」と述べています。この双方向のフィードバック文化を定着させることで、組織内に信頼関係が生まれ、オープンな学習環境が整います。
3.2 自己実現ビジョンに紐づいたコミュニケーション
効果的なフィードバックのためには、「相手の自己実現ビジョンに紐づいたコミュニケーションを意識すること」が求められます。相手の将来の可能性や目標を理解し、それに関連したフィードバックを行うことで、受け手はより前向きに受け止められます。
3.3 チーム全体での共有
最後に、フィードバックの内容はチーム全体で共有されることが有効な場合もあります。安斎氏は、「内容によっては、他のメンバーにも共有されていた方が、チームづくりの観点でプラスになるケースもある」と述べています。これにより、チーム全体で課題や成功体験を共有し、組織全体の学びを深めることができます。
取り込みの指針
ポテンシャルフィードバックの話は参考にしていて、過去にも実施した事があります。ただ、そのフィードバックの効果については深い関係性が重要とも考えていて、単に実施すればよいというものでもないと感じました。(やったこと自体はとても良かったですが・・・)
また、冒険的なフィードバックに求められる「内的動機に寄り添い、しかるべきタイミングや場所を見極めて、相手のものの見方を広げてあげる」という在り方についても、本当にその通りだと共感しています。しかしながら、実際にそれを自分が実行することを考えると、非常に高いハードルを感じてしまいます。
フィードバックの質を高めるためには、チーム全体としてのミッションと個人のミッションをしっかりと関連付けることが不可欠です。それぞれのメンバーが個人として探究したいテーマや達成したい目標を持っている一方で、チームや組織全体が掲げるミッションも存在します。両者を結びつけることで、「このフィードバックは自分の成長だけでなく、チーム全体の成果にもつながっている」という実感をメンバーが得られるのではないでしょうか。
そのため、まずは組織としてのミッションと個人の探究テーマの関連性を可視化し、共有する場を設けることが重要だと考えています。現在3カ月に1回実施しているGCLTの会をより効果的に実施できるよう検討していきたいと思っています。
加えて、フィードバックをより組織全体で活用していくためには、リーダーへのフィードバックを活性化させることも必要です。リーダーが率先してフィードバックを受け入れる姿勢を見せることで、チーム全体に「お互いにフィードバックをし合うことは当たり前であり、成長のために必要な行動である」という意識を浸透させることができます。
特に、リーダーに対してはもっと鋭角的で、時には厳しいフィードバックを行うことも必要だと感じています。リーダー自身がそのフィードバックを受け止め、成長していく姿を示すことで、組織全体にポジティブな影響を与えることができるはずです。リーダー自身がしなやかなマインドセットで変容を見せることが組織のフィードバック文化醸成には大事なのではと思っているので、リーダーへのフィードバックを行う会はぜひやりたいと思います。