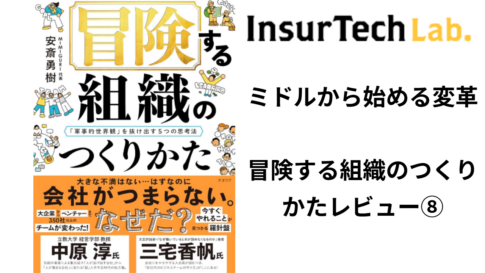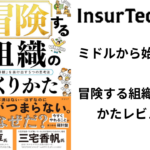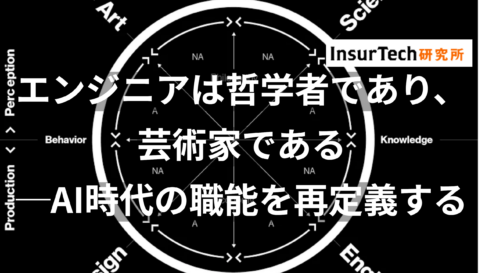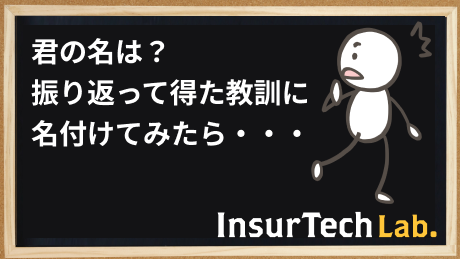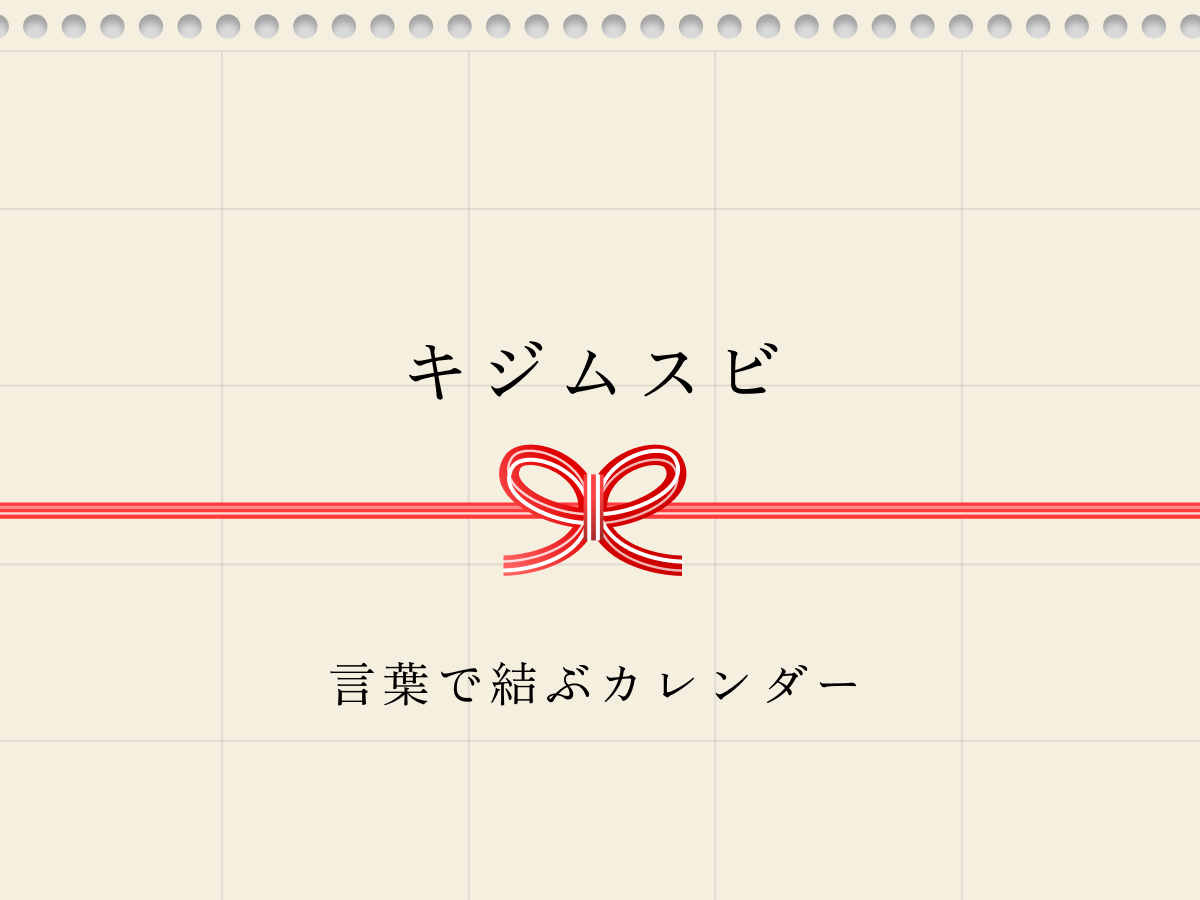安斎勇樹さんの『冒険する組織のつくりかた』から、今回は「KEY8『共通体験』のリフレクションで、チームの学びを深める」について考えます。
ちなみに前回の記事はコチラです。
チームとしての学びを深めるために欠かせないリフレクションの重要性や実践方法について、本書の内容を引用しつつ紹介します。
安斎氏は本書の中で「メンバーと共にした体験を振り返り、それに意味を見出すという作業が欠かせない」と述べています。ただ忙しく仕事をこなすだけでは、チーム内でその体験を「共通体験」として捉えることができず、学びが深まりません。
このことはアジャイルをやっている身からすると普通の内容でしたが、社内全体で出来ているか?またチームのふりかえりを組織知として共有できているか?というと、全くできていないので、参考になりました。
1. リフレクションを「共通体験」に昇華させる方法
1.1 社内公開イベントとしてのリフレクション
本書では、チームでのリフレクションを「社内公開イベント化」することが推奨されています。安斎氏が所属するMIMIGURIでは、「まいに知たんじょうび」という社内番組を実施しており、プロジェクト終了後にチーム全員が出演し、自分たちの「共通体験」を語ります。
この取り組みによって、単なるチーム内の振り返りにとどまらず、組織全体での「共通体験」としての認識が広がったそうです。安斎氏は、「この公開リフレクションが社内で大好評を博した」と紹介しており、学びを組織全体に浸透させる力強い手法であることが分かります。
私たちも昨年、組織が設立してからの2年間をふりかえるイベントを実施し、チームを超えて共有することで、その効果を実感しました。
ただ、2年間のタイムラインだとちょっと長すぎる為、もう少しライトにチームでの振り返りを共有する仕組みは考えたいと思います。3カ月に1回の、ふりかえり&キックオフのタイミングで、チームでの「ふりかえり」の共有の時間をとっても良いと思いました。
1.2 KMQTによる効果的なふりかえり
さらに、MIMIGURIでは「KMQT(Keep, Moyomoyo, Question, Try)」という独自の振り返りフレームワークを使用しているそうです。このKMQTの特徴は、「モヤモヤ(Moyomoyo)」をあえて共有するステップを設けている点です。 安斎氏は、「モヤモヤを共有することで適応課題を早期に発見できる」と強調しています。
我々も「もやもや」の共有は大事にしていて、ふりかえりのフレームに結構「M:Moyatto」を共有できるような意識を良くしています。
普段から、そういった「もやっと」を表明する意識をしておくと、モヤモヤする点はないか?とすぐ質問できたり、表明しやすくなるため、非常に良いと感じています。
ちなみに、昨年度のふりかえりカンファレンスでもKMQTについては公演されていましたので、スライドを載せておきます。
2. 学びを深めるリフレクションの実践について
我々もチームでのふりかえりについては十分出来ていると考えていますが、そのチームでのふりかえりを表出して結合する場については弱いと感じています。今は時々実施する登壇形式での共有やOSTでの共有といった形で進めてはいるものの、もう少しライトに自動化できる仕組みが必要と思います。
とりあえず、3カ月毎にライトにプロジェクトでのチームでの振り返りを共有する場を作ってみたいと思いました。
企保的にはYWTのフレームを少し変えて、「やったこと、わかったこと、もやもやすること、今後にむけて」をチームメンバーで書いてもらいチームから他のチームに共有するという場を持ちたいと思いました。
読んでいただきありがとうございました。