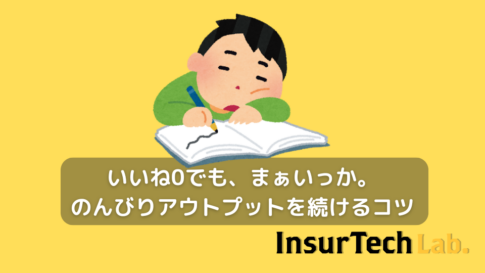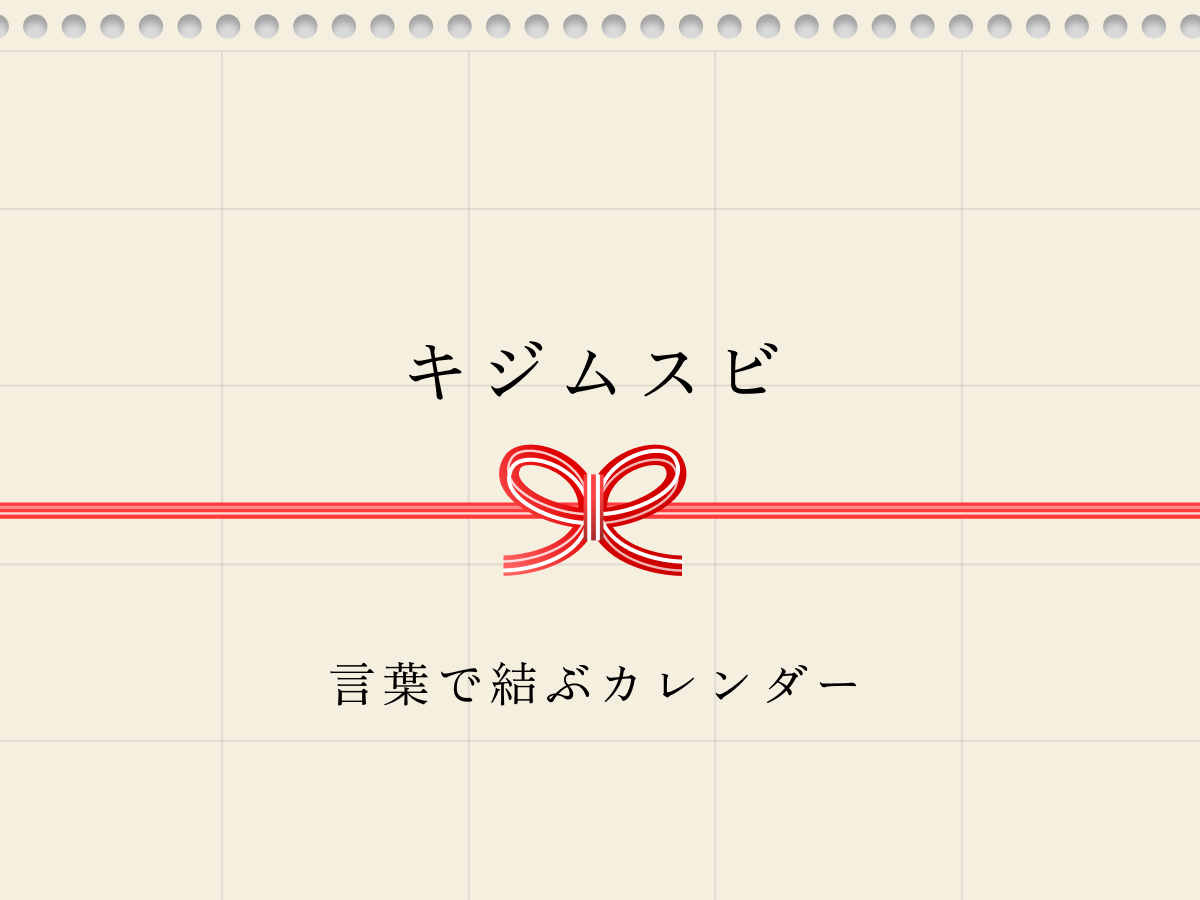昨日に引き続き、安斎さんの「冒険する組織のつくりかた」をもとに、これまで実践した施策を振り返り、今後の方向性を整理します。本日は『KEY17「ボトムアップの「勉強会」から、変革のうねりを全社に広げる』です。
ちなみに昨日の記事はコチラです。
1. はじめに:勉強会は組織変革の起点になりうるのか?
組織を変えようとするとき、トップダウンの経営主導のアプローチだけではうまくいかないことがあります。組織の文化を変えるには、現場からのボトムアップの動きも欠かせません。
では、ボトムアップ型の変革を成功させるには、どうすればよいのでしょうか?安斎勇樹さんの『冒険する組織のつくりかた』 では、その鍵のひとつとして「社内勉強会」に注目しています。本書では、社内勉強会が単なる学習の場にとどまらず、組織を変革するムーブメントを生む可能性について詳しく述べられています。
私たちもまた、社内勉強会を通じて組織に変化をもたらせるのではないかと考え、「学びフェス」 という取り組みを実施しました。本記事では、その実践を振り返り、今後どのように学びを広げていくべきかを考えていきます。
2. 社内勉強会が変革の起点となる理由
『冒険する組織のつくりかた』の KEY17 では、ボトムアップ型の変革を進めるための社内勉強会の役割について、いくつかのポイントが強調されています。
- 経営陣の視界に入ることが鍵
勉強会が現場でどれだけ活発に行われていても、それが経営層に認識されなければ、組織全体の動きにはなりません。本書では、経営陣の視界に入れるタイミングをどう作るか が重要であると述べられています。
- 課題ありきではなく、好奇心が出発点
経営主導の変革は、「この課題を解決しよう」という明確な目的を持って進められることが多いですが、ボトムアップのアプローチでは、必ずしも明確な課題がなくてもよいとされています。
つまり、学びの場は「これを解決しなければならない」という強制的なものではなく、「ちょっと気になる」「面白そう」という純粋な好奇心からスタートしてもよいのです。
むしろ、現場での学びはこうした柔らかな動機から始まることが多く、それがやがて組織の課題解決につながることもあります。
- 参加者を「変革の仲間」にする
社内勉強会の大きな課題のひとつは、参加者が固定化しがち という点です。本書では、「お客さん」から「変革の仲間」へと意識を変えていくことが重要だと書かれています。
つまり、「学びの場に来る人が、単なる受講者ではなく、組織を変える主体になる」という意識を持たせることが、勉強会の影響力を高める鍵となるのです。
3. 「学びフェス」の実践:変革の起点になれたのか?
私たちは、アジャイルやプロダクト開発に関する社内勉強会を毎週開催してきました。しかし、参加者は10人前後で安定していました。勉強会自体はカンファレンス動画視聴が中心で、負荷低く実施でき、自分達の学びに繋がる手ごたえを感じていたので、取組自体には満足していました。しかし、ボトムアップの変革という意味では、グロースに課題を感じていました。
そこで、「学びの場をより広く認知させ、影響力を持たせるにはどうしたらいいか?」と考え、社内の目を引くイベントとして「学びフェス」を企画しました。
「学びフェス」の特徴
- 3カ月に1カ月間、毎日勉強会を開催
→ 短期間で高頻度の開催を行うことで、社内の認知度を高める狙い。 - 開催時間を固定せず、午前・昼休み・夕方などで実施
→ 参加のしやすさを向上させ、異なる層の人にリーチする。 - 負荷を抑えた運営
→ デイリーで実施できるレベルの運営にすること、持続可能な運営にすることを中心に、準備や実施のやり方を一定のルール化するだったり、勉強会の講師をやってくれる方を公募制にして仲間を増やす など、継続可能な体制を意識する。 - 人事領域とも連携
→ 勉強会を単なる「個別の学習活動」ではなく、組織全体の成長戦略に絡める。 - 社内メディアを活用して、毎日情報発信
→ 社内のカルーセルなどで発信を繰り返す等、告知も重視
結果として、社内での勉強会の認知は高まり、「学びフェス」というイベントを多くの人が知る状態になりました。
4. これまでの成果と課題
成果
- 新しい層の参加が増えた
勉強会講師の方が新たな参加者を連れてくるなど、これまで参加したことがなかった層が、足を運ぶようになりました
- 勉強会の認知が高まり、組織的な取り組みとして評価された
社内メディアを通じた情報発信の結果、「学びフェス」の存在が広く認識され、社内の優秀表彰を受賞するまでになりました。
課題
しかし、まだまだ「固定メンバーだけで回っている」状況は解消できていません。
- 勉強会の存在を知っていても、自分ごととして捉えられない
周囲へのヒアリングでは「学びフェス」についてはかなりの方が知ってはいるものの、そもそも自分には関係ないものと捉えられ、「参加しよう」と思うまでには至らないことが分かっています。
- 一部の固定ファン入るものの、増えていかない(特に若手が入ってこない)
また、参加してくれた方もほとんどのメンバーが数回の参加でとどまりコアなファン層はほとんど増えていない状態です。特に中堅/若手が増えないという問題があります。
5. 次のステップ:勉強会をどう進化させるか?
次年度は、「固定ファンを増やすこと」 をテーマに勉強会を継続していきます。そのために、以下の取り組みを進める予定です。
- 勉強会のWhyをもっと語る
本の中でも、『勉強会の冒頭で、何を勉強するのか(What)だけでなく、なぜこの勉強会をやっているのか(WHY)についてもストーリーテリングする)という事が書かれています。現在は運営者の趣味が強い勉強会なので、今後、WYHやストーリーを作ってアピールする動きが必要と感じています。
- 他の事業部とのコラボイベントを増やす
「この勉強会は自分には関係ない」と思っている人に対し、他の事業部とコラボすることで、「身近な人も参加している」という意識を生み出すことを狙います。
- 参加しやすい仕掛けを作る
管理職層からチームメンバーに案内してもらう等、ちょっとずつ参加しやすい仕組みを作ることが大事と考えています。
- 経営層の後押しを得る
今回の優秀表彰を活かし。経営層からの後押しを得ることで、より組織的な活動へと発展させることを目指します。
- あまり広げることを意識しすぎない
とはいえ、コミュニティについては急に広げると文化が崩れていくという課題もあると感じています。現在はコアなメンバーの総量が少ないため、まずはコアな仲間をちょっとずつでも見つけていく事を大事に、継続を是として少しずつ増やしていきたいと思います。
6. まとめ:ボトムアップの学びをどのように広げるか?
「学びフェス」を通じて、勉強会が組織変革の起点になりうることを実感しました。しかしながら、起点からどう育てていくかという点はまだ未知の冒険なので、次年度からさらに、実験的な取り組みを進めていきたいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。