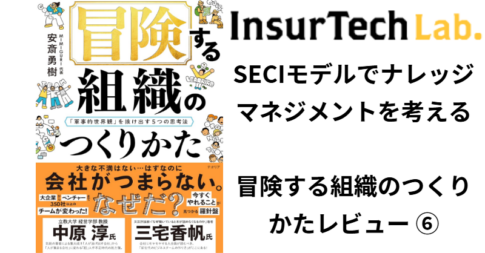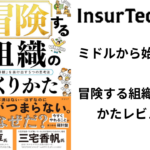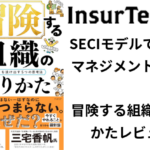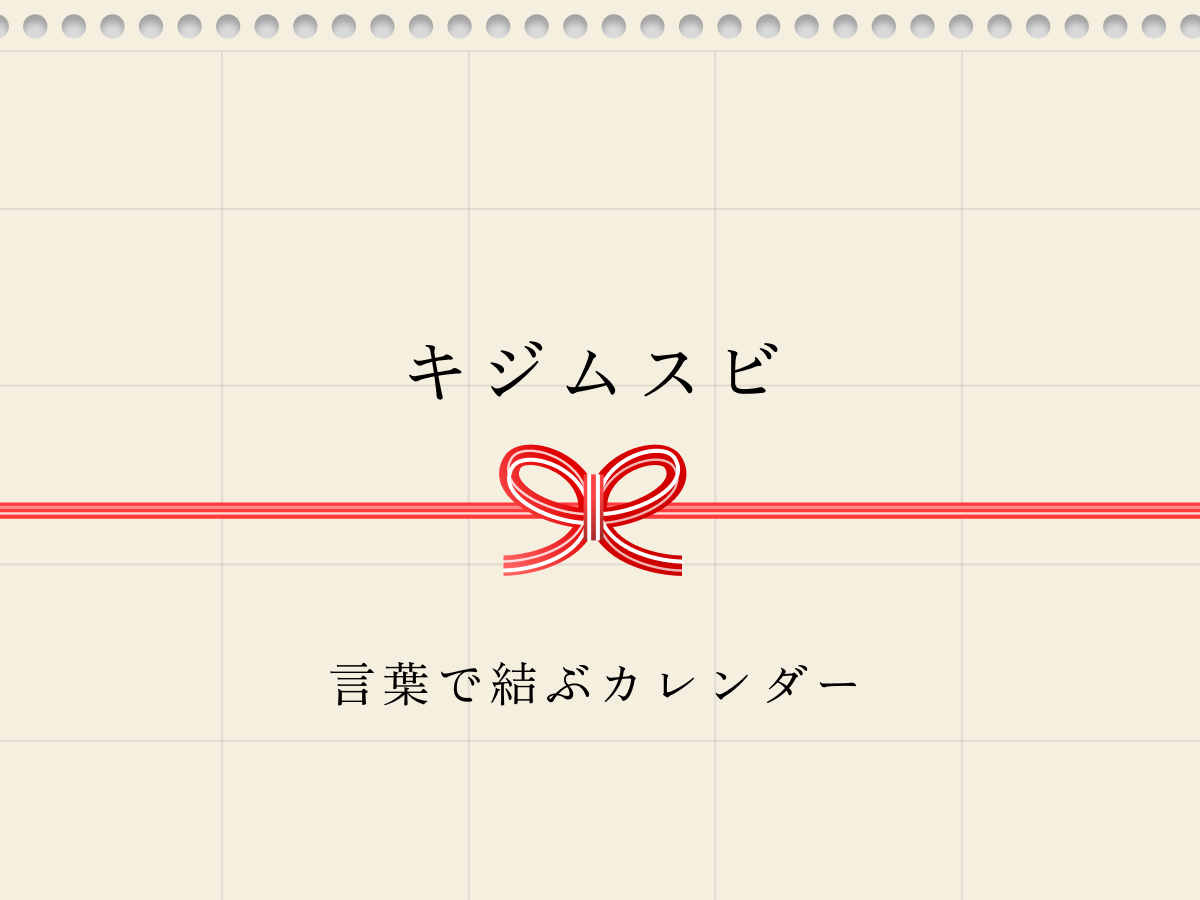昨日に引き続き、安斎さんの「冒険する組織のつくりかた」をもとに、これまで実践した施策を振り返り、今後の方向性を整理します。本日は『KEY1 現場の目標にこそ『追いかけたくなる意味』を込める』です。
ちなみに昨日の記事はコチラです。
1. 目標設定における「意味」の喪失
現場レベルの目標は、しばしば組織全体の大目標を細分化した結果として与えられます。安斎さんはこれを「大きなピザを細かく切り分けた末に、小さなトマトの切れ端だけを『あなたのピザです』と渡されるようなもの」と表現しています。
このような目標は、組織にとっての「機能的な意味」はあっても、個人やチームにとっての「精神的な意味」を欠いてしまいがちです。
特に目標が経営レベルから現場に降りていく過程で、なぜその目標が重要なのか、何のために達成するのかといった「意味」が失われてしまいます。その結果、目標が単なる作業のリストになり、メンバーが主体的に取り組む意欲を失ってしまうことがあります。
2. 「追いかけたくなる意味」を込めるために
ALIVEな目標設定
安斎さんは、現場の目標に「追いかけたくなる意味」を込めるための法則として「ALIVE」を提唱しています。
- Adaptive(変化に適応できる)
- Learningful(学びの機会になる)
- Interesting(好奇心をそそる)
- Visionary(未来を見据える)
- Experimental(実験的である)
ALIVEな目標は、単なる業務遂行の指標ではなく、メンバーがワクワクしながら取り組めるものです。例えば、短期目標に好奇心をくすぐる「問い」を埋め込むことで、現場のメンバーが意味を見出しやすくなります。
「問い」を通じた対話の場づくり
目標に「問い」を埋め込む際、リーダー一人が考え込むのではなく、チーム全体で対話することが重要です。「なぜこの目標を達成したいのか?」「この目標を達成したらどんな未来が見えるのか?」といった問いをチーム全体で共有し、それぞれの視点や価値観を反映させることで、目標に対する納得感とやりがいを高めることができます。
3. 我々における現在の課題と今後の方針
私たちの組織は、これまでR&Dに特化した組織として、長期的なビジョンを中心に活動してきました。そのため、短期的な売上目標に縛られることなく、ALIVEな目標に取り組めてきたと感じています。
しかし、今年はこれまでと状況が変わりました。短期的な売上目標を達成することも、組織の成長に欠かせない要素となったのです。
当初、私たちは「売上目標」とは別に、「組織的な目標」を立てようと試みました。しかし、そのプロセスにおいて、「売上目標に対する意味付けや問い」を十分に意識できていなかったことに気づきました。
結果として、売上目標については、メンバーにはあまり意識させない形で進め、長期的なビジョンと整合しきれていない中、矛盾を抱えながら進めていたのが今年の状態でした。
しかしながらだんだんと売上目標が具体的で大きくなってくる中で、組織としても目標を意識した運営が必要になってきいています。受委託型のビジネスで、我々のチーム自体もプロパー/パートナー混ざって組んでいる中で、この「売上」を目標に入れることはかなり難易度が高いと感じています。しかしながら、何らか意味付けのある「問い」を今年は立てていかないといけないと考えています。そうなると必然的に、自分の問いだけでなくパートナーさんやパートナー企業を巻き込んでの問いの設定がポイントとなってくるでしょう。
また、売上を上げるためにはお客様への受託型のビジネスが現状現実的ですが、受託型のビジネスでよりお客様に価値を提供していく上では、今まで実施しているプロダクト開発のケイパビリティが重要だと考えています。
「受託型のビジネスで売上を上げるためには、どうしてもR&D活動の時間を削る必要がある。しかし、果たしてそれでいいのだろうか? この問いに私たちは悩み続けています。
私が参考にしているのは、デンマークの建築家ビャルケ・インゲルスが提唱する「YES is MORE」という考え方です。
「YES is MORE」は、二者択一を迫られる状況においても、「どちらも選ぶ」ためのクリエイティブな解決策を模索するアプローチです。
イメージでしかない、売上目標の達成とプロダクト開発の探究を受委託型のチームで両立させる挑戦に、この1年取り組んでいきたいと考えています。
読んでいただきありがとうございました。