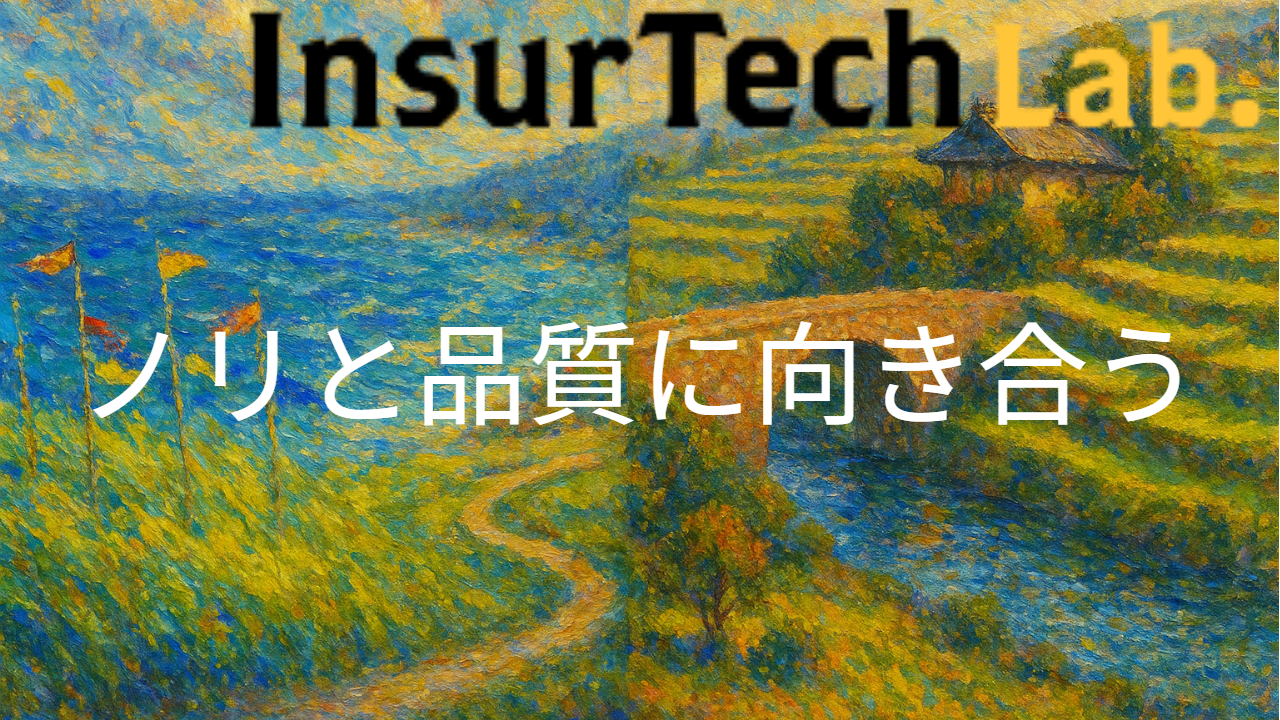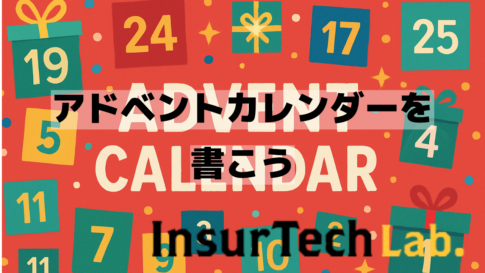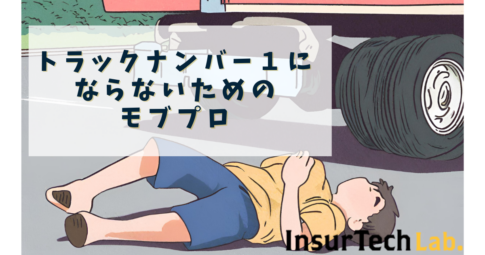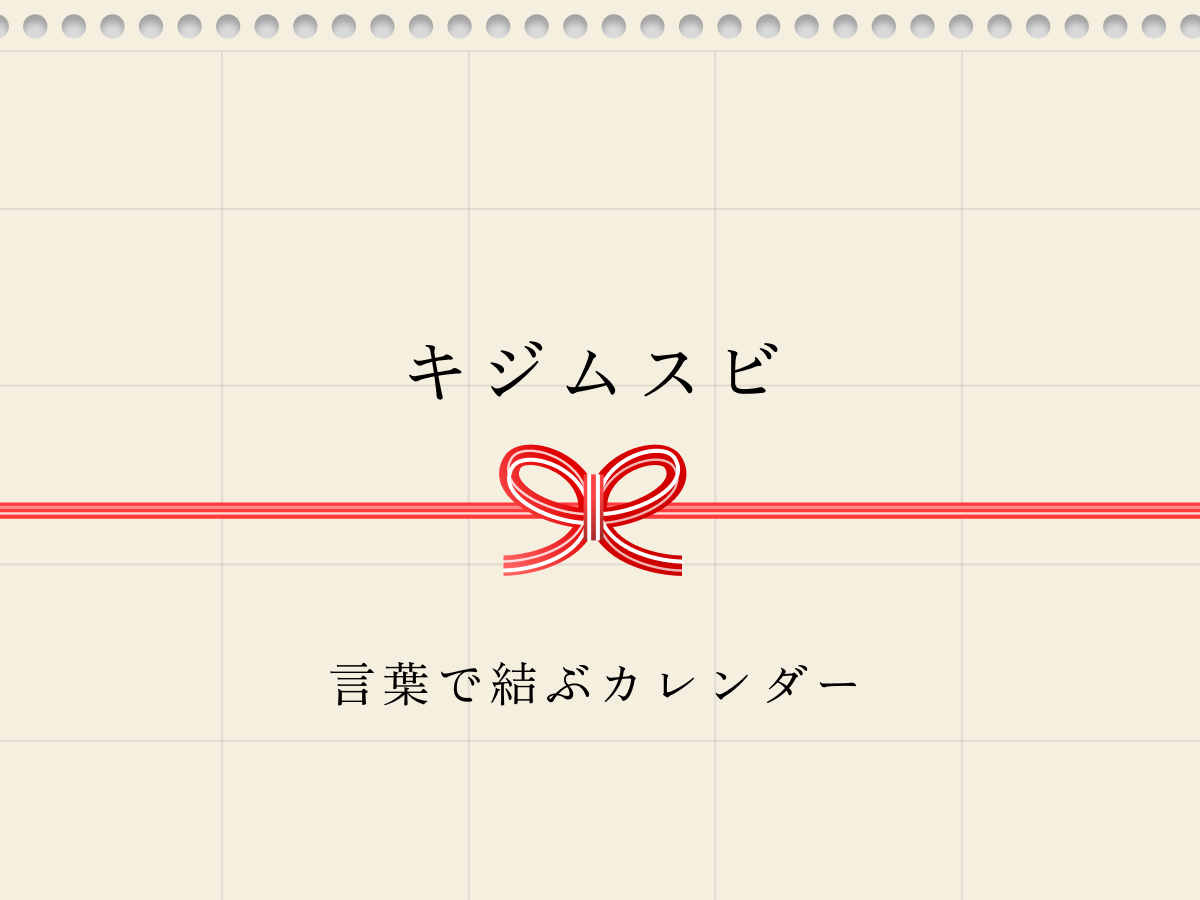このクォーター、私たちはチームテーマとして「ノリと品質」を掲げました。背景には、ラボが一定の成長フェーズに入り、実開発のアジャイル支援や、ユーザーと共創するプロダクト作成といった“実戦”が増えてきたことがあります。
これまで私たちの強みは「目的指向のビジョニング」や「仮説検証スキル」でした。しかし現場の難易度が上がるほど、勢いを生む力(ノリ)と、再現できる説明と作り込み(品質)の両方が求められます。
片方だけではどうしても伸び悩む――その手応えが出てきたため、今期は意図的にこの2軸を鍛えることにしました。
- ノリ:場の設計と相互作用(リーダーシップ/フォロワーシップ)によって生まれる推進力。巻き込み・合意形成・一歩目の速さを指します。
- 品質:いわゆる品質ですが、「なぜそうしたか」が読み取れる設計・記録等の説明責任に関する部分も強いです。抽象(意図・価値仮説)と具体(実装・テスト)が往復できることを重要視します
ノリについて
ノリについてはリーダシップ、フォロワーシップを高められないかいくつか実験してきました。
① 期間限定でプロダクトオーナー(PO)業務を付与する
主体的に考えられるようなストレッチ目標を設定し、意図的にリーダーシップを発揮せざるを得ない状況をつくりました。
② ①の状況下で、チームや個人がフォローできるようにする
スキルが足りないメンバーも含めて、周囲が支える動きを意識して整えました。
(※ここでのフォローは、情報共有・下調べの手伝い・説明の支援など、負荷を分け合う行動を指します)
上記のような取組を実施してきました。劇的な変化とまではいかないものの、狙い通り、メンバーがこれまでよりも頑張る場面が増え、その頑張りを周りがフォローする動きも見られたと感じています。
また、場の設定の重要性を強く実感しました。
もともと、リーダーシップやフォロワーシップは個人の特性に左右されやすいため、テーマに掲げても変化を観察しにくいのではないかと考えていました。そのため当初は、繰り返し伝えることや学習の機会を重視していました。
しかし、対話のワークショップを繰り返す中で、ビジョンを共有し、心理的安全性が高いチームであれば、適切な場の設定そのものが大きく効くと考えるようになりました。具体的には、メンバーが現状の課題を表明しやすくなり、それに対してチームが自然にサポートへ動ける状態が生まれます。
(※「場の設定」とは、たとえば目的の共有、発言のルールやフレームの明確化などを指します。なお、自然に任せすぎず、スクラムマスター的な介入は必要だと考えています)
良いふるまいは人の問題だけでなく、場の設定にも問題が大きいと考えており、今後は、こうした場の設計に、より力を入れて取り組んでいきたいと思います。
品質について
もう一つのテーマである品質については、品質に関する勉強会を定例で実施するなど、少しずつ取り組みを進めています。ただし、浸透はなかなか難しいと感じています。
浸透が難しいと感じるのは、たとえば次のような理由が背景にあります(あくまで例です)。
- 概念的に必要性は分かるものの、現場での必要性を感じにくい
- 日々の開発で後回しになりやすく、習慣化までに時間がかかる
- 成果が見えづらい取り組みもあり、効果を実感しにくい
個人的には、社外との接点を増やし、知見が自然に入ってくる状態を作ることが大事だと考えています。それは、上記品質の視点は新たな考え方やメンタルモデルが必要だと思っているからです。
外からの良い型や事例が継続的に流入してくるか——その仕組みづくりで対応できないか、引き続き検討していきたいと思います。
イメージとしては、外で得た学びをチームに持ち帰り、共有 → 小さく試す → 振り返る→発信するの流れが自然に回ることを目指します。今はまず、定例の勉強会を土台に、社外とのつながりを増やす設計を重ねていく方針です。
3Qに向けて
また、10月以降ですが、上記しているノリと品質要素は引き続き大事にしますが、今回観察できた、できてないメンバーをフォローするということだけでなく、できているリーダー層をフォローできるようにするという点を何とか実現できないかと思っています。
リーダー層は一定孤独だったり、またスキル面でメンバー層とリーダー層に見えない壁があるような雰囲気がありますが、そういった壁を飛び越えたフォロワーシップを形成できれば、チームでの知識移転も進み、学習は進むと考えています。
社内を超えての学習に関するムーブメントをどう起こせるかもポイントになると考えており、そういった施策を軸に3Qの目標や施策をまた考えていきたいと思います。
読んでいただきありがとうございました。
10月以降も、ノリと品質の要素は引き続き大事にしていきます。あわせて、今回の観察から、「できていないメンバーをフォローする」だけでなく、「できているリーダー層をフォローする」という点を、何とか実現したいと考えています。
出来ていないメンバーのフォローはチームのベースとして非常に重要なことだと思っています。ただチームのパフォーマンスを上げるためにはリード層をさらに強める必要があり、リードメンバーと切磋琢磨して進めていくような動きが大事だと考えています。
リーダー層は一定の孤独があり、またスキル面でもメンバー層とのあいだに見えない壁が存在する雰囲気があります。ここで言う「壁」は、前提や言葉の使い方、期待される役割の違いなどから生まれる心理的な距離のイメージです。
この壁を飛び越えたフォロワーシップが形成できれば、チーム内での知識移転が進み、学習の速度も上がると考えています。
さらに、社内を超えた学習のムーブメントをどう起こせるかもポイントだと捉えています。社外のコミュニティや勉強会、ワークショップ等との接点を設計し、外から入ってくる知見を自然に循環させられる導線を検討していきたいと思います。
これらを軸に、3Q(10–12月)の目標や施策を改めて考えていく方針です。
※具体的な進め方はこれから検討しますが、たとえば「リーダー層の判断プロセスを共有・ディスカッションする場」「壁をまたいだ対話の導線」「社外で得た学びの持ち帰りを促す仕組み」などの観点を想定しています。
読んでいただき、ありがとうございました。