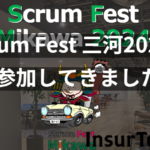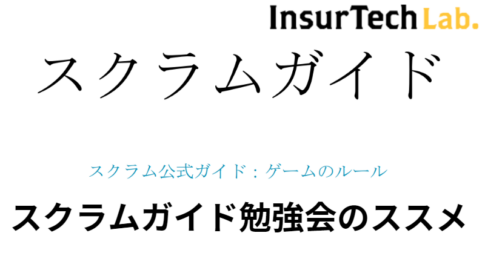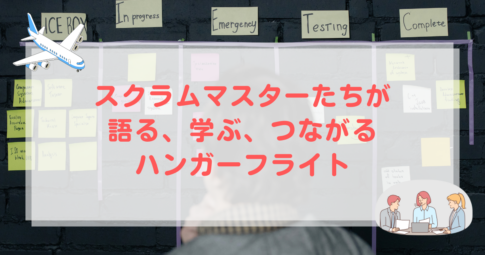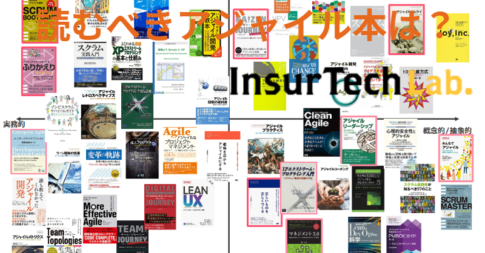9/13(金)、9/14(土)にスクラムのイベントであるスクラムフェス三河が愛知県豊橋市でありました。
現地参加したかったものの、気づいた時には現地チケット完売で、オンライン参加したので感想を書きます。
(この記事は20242Qアドベントカレンダー12日目の記事で書いています)
参加しての感想
感想を一言で言うと、いくつかの熱いセッションを聞いて、あぁ、現地参加できればよかった。。。といった感想でした。
スクラムフェスとは
スクラムフェスは毎月(?)全国各所、場所を変えて実施されているスクラムのお祭りです。
発表者が、スクラムを導入・実施する上で得た知見などを熱く語り、参加者は現地またはオンラインチケットを買ってフェスに参加し、発表者の発表を聞くことになります。
発表は誰でも参加が可能ですが投票制で、発表内容が事前に告知され、ネットで投票の多いものが採用されます。当日は、複数の発表が同時に進行するため、参加者は自分が見たい・聞きたいセッションを選んで見ることになります。
現地参加の醍醐味としては、連日のイベント終了後に催される自由参加の懇親会や、現地でしか味わえないお弁当などが魅力の一つとなっています。
感じた違和感
私はこれまで何度スクラムフェスにオンライン参加していましたが、7月の金沢で初めての現地参加デビューを果たしました。8月にはスクラムフェス仙台があったものの参加せず、今回は現地参加後、初のオンライン参加となりました。
9/13(金)夜の基調公演は、用事があって見ることができず(あとで参加者だけに限定公開されるアーカイブで見ようと思う)、9/14(土)朝から参加となり、これまで通り、DISCORDに表示されているURLを叩いて、ZOOMに参加しました。しかし、あれ?という違和感が最初にありました。
この違和感がどういう違和感か分からないまま、セッションの視聴を進めると、違和感の理由がだんだん分かってきました。
違和感の理由
違和感の理由は、パソコンのモニター越しに見える四角い世界からは、ワイワイする会場の360°の雰囲気や、発表者の熱量、発表者と参加者、そして運営者から成り立つ「場の雰囲気」が十分に感じることができないことでした。
例えるなら、「国内有名花火大会の中継をテレビで見ている」ような感覚で、あの、浴衣がまぶしい風情のある会場。花火を楽しみに待つ雰囲気や、花火が開く時に体で感じるドンという音や、子供の喜ぶ声。リアルに空に映える美しい花火。
どれもがオンラインでは十分感じることができないことを現地参加することで知ってしまいました。
刺さった発表
その状況の中でも、いくつか刺さった発表があったので、感想を書きたいと思います。
OSTという文化を組織に根付かせてみた
この発表は、組織間の交流が断絶している社内状況を改善すべく、過去にOSTを経験した発表者が、全く意図してなかった運営者になり、交流を目的としたOST(Open Space Technology)を社内で実施・成功させ、そこでの運営体験や繰り返しOSTを実施することで起きた変化についての話でした。
本来、OSTは参加者主体のイベントで、運営があまり関わらないのですが、あえて「普段一緒に仕事したことない人と繋がりを作る」を目的として打った運営の施策が、狙った効果になったり、最終的にはOSTが成功し、社内に広がっていく様子が目に見えるようでとても面白かったです。あと、関西弁の発表もテンポがよく聞きやすかったです。
私自身のOSTに置き換えると、盛り上がりが少ないのは、何のためにOSTやるのか目的が曖昧だったり、目的達成のための運営(場の設計)が足りないのかなと考えさせられる発表でもありました。
必要なのは客観性。組織変革をもたらす、より良い「対話」を生み出すための活動
このセッションは、ワークショップデザイナーという役割のアンジェラさんとケンシロウさんが、組織内での対話を促進するために行っている活動を紹介するものでした。
2人は社内で、これまでマネージャーが運営・実施してきた会議から、ファシリテーションや会議運営を代行することにより、マネージャーも会議の参加者になって組織の対話を促進する役割を行っているということでした。
驚いたのが、発表がワークショップから始まったことでした。
ワークショップでは対角線と、縦横十字に線が書かれた正方形から、線に沿っていくつ漢字が書けるかという内容で、最初は1人で考えて、次は隣と2~3人で一緒に考えてみるといったものでした。個人とグループ協力による成果の違いではグループ協力の方がはるかに効果があり、それを体感するワークショップでした。
また、会議設計では、マネージャーより会議支援を受けた際は、事前に会議の設計書を作成しマネージャーより承認をもらうという話で、設計書を見せてもらいましたが、目的の明文化や分刻みのシナリオなど緻密さにびっくりしました。
自身のチームでは、打ち合わせは発散が多く、どこに向かっているのか途中でわからなくなることが多いですが、目標の明確化や会議設計が重要と気付かされました。
まとめ
アジャイルでも運営設計は重要だなと感じる2つのセッションが刺さりました。
また、現地イベント参加の楽しみを認識した今、この楽しみを皆に広めて「場の共有」の重要性を共感できたらと思ったスクラムフェス三河でした。